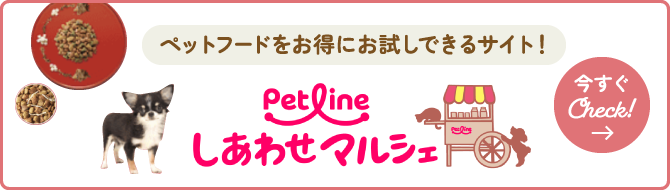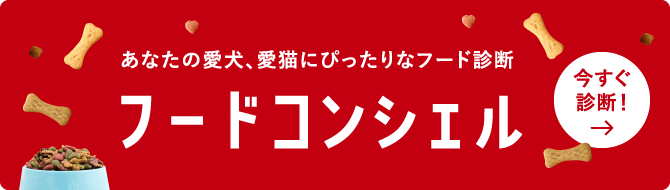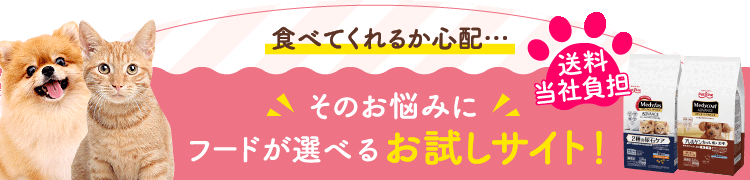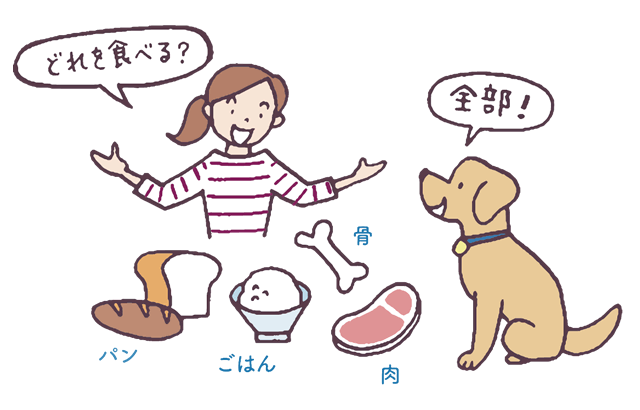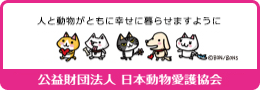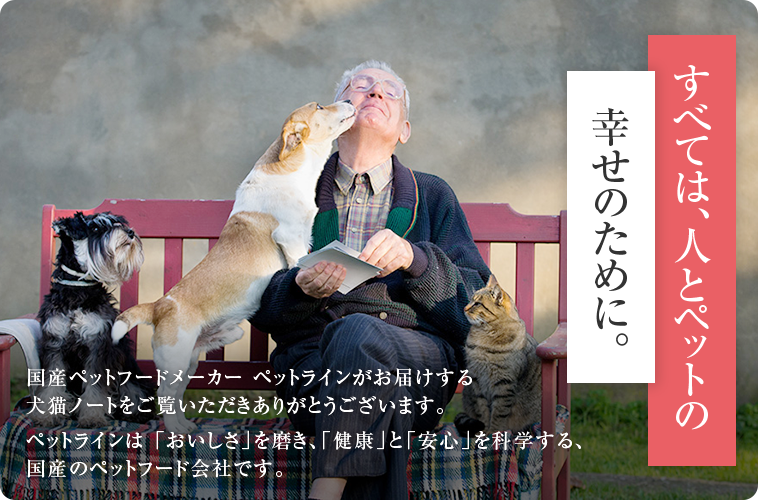犬の年齢は人間で言うと何歳?平均寿命や長生きするために気を付けたいポイントを紹介
- 公開日:

大切な愛犬が人間の年齢で言うと何歳になるのか気になっている飼い主さんも多いのではないでしょうか。この記事では、犬の年齢を人間の年齢に換算すると何歳になるのか犬の大きさごとの平均寿命や、いつまでも元気に長生きしてもらうためのポイントを紹介していきます。
更新日:2025年7月28日
犬の年齢早見表
犬の年齢を人間で言うと何歳になるのかを知っていれば、まだまだ遊び盛りなのか、そろそろ老犬に差し掛かっているのかなど、愛犬の状態や気持ちを理解しやすくなるでしょう。以下は犬の年齢を人間の年齢に換算した時の早見表です。
小〜中型犬は生後2年で人間では24歳ほどになり、3年目からは毎年4つずつ歳をとっていくと考えられています。大型犬は生後1年では人間の12歳ほどになり、その後は毎年7つずつ歳をとっていくと考えられています。
| 犬の年齢 | 人間に換算した年齢 | |
|---|---|---|
| 小〜中型犬 | 大型犬 | |
| 1歳 | 15歳 | 12歳 |
| 2歳 | 24歳 | 19歳 |
| 3歳 | 28歳 | 26歳 |
| 4歳 | 32歳 | 33歳 |
| 5歳 | 36歳 | 40歳 |
| 7歳 | 44歳 | 54歳 |
| 10歳 | 56歳 | 75歳 |
| 12歳 | 64歳 | 89歳 |
| 15歳 | 76歳 | 110歳 |
| 20歳 | 96歳 | - |
※【出典】:環境省「飼い主のためのペットフード・ガイドライン 」より
犬の年齢を人間の年齢で表すときの計算方法
人間換算の犬の年齢を表すためには、大型犬と小型・中型犬それぞれの計算式から求めることができます。愛犬の現在・未来のライフステージを想像することで、健康管理に役立てていきましょう。
大型犬の計算式は12+(大型犬の年齢-1)×7
大型犬の場合の計算式は「12+(大型犬の年齢-1)×7」です。
例えば、3歳の大型犬を計算式に当てはめると「12+(3-1)×7=26」で26歳となります。
大型犬は老化が早く進む傾向にあるため、早めの時期からケアをしていくことが重要です。
小型・中型犬の計算式は24+(小型犬の年齢-2)×4
小型・中型犬の計算式は「24+(小型犬の年齢-2)×4」です。
例えば、3歳の小型犬を計算式に当てはめると、「24+(3-2)×4=28」で28歳となります。
小型犬の成犬期の成長は緩やかになります。アクティブな期間が長くなるので、元気なシニア期を迎えられるよう健康状態をしっかり確認していくことが大切です。
ライフステージの考え方
人間と同様に、犬もライフステージによって気を付けるポイントが変わってくるため、ライフステージを把握しておくことは大切です。犬種や犬の大きさによって差はありますが、生後〜1年未満であれば子犬、生後1年〜6年ほどは成犬、7年を過ぎたあたりからシニア期に入ってシニア犬へとなっていきます。
愛犬の年齢が分からない時
愛犬が人間で言うと何歳くらいなのか知りたいけれど、保護犬などの場合はそもそも愛犬の年齢が分からないかもしれません。愛犬の年齢を知ることは、飼い主さんにとっても、適切な健康管理やお世話をしてあげるためにとても重要なポイントになります。犬の年齢は、歯や歯茎の状態、体つきや顔つき、毛並みや足の状態からある程度推察できますので、年齢がわからない場合は動物病院で獣医師に判断してもらうと良いでしょう。
犬の平均寿命は何歳?
犬全体としての平均寿命は14.90歳(2024年時点)と言われています。興味深いことに犬の寿命は2010年以来伸びており、2010年時点での平均寿命と比べて2024年の報告では1.3歳も伸びているという調査結果が出ています。これは飼い主さんの愛犬に対する日々の心がけや、ペットフード、動物医療の進歩の成果と言えるでしょう。
平均寿命も犬の大きさごとに異なっており、身体の小さい犬ほど寿命が長く、大きい犬ほど短い傾向にあるということが分かります。
| 犬の大きさ | 平均寿命 |
|---|---|
| 超小型犬 (チワワ、トイプードル、ポメラニアン等) |
15.13歳 |
| 小型犬 (シーズー、パグ等) |
14.78歳 |
| 中〜大型犬 (柴犬、ビーグル、コーギー、レトリバー等) |
14.37歳 |
※【出典】:一般社団法人「ペットフード協会 」より
少しでも健康に長生きしてもらうためのポイント
飼い主さんとしては、大切な家族の一員である愛犬と少しでも長く一緒に過ごしたいもの。愛犬がいつまでも健康で元気に長生きしてくれるよう、飼い主さんにできることを5つご紹介します。
①食事管理
犬は年齢によってそれぞれ必要とするカロリーや栄養素が異なります。愛犬が現在どのライフステージにいるのかを把握し、それに合ったバランスの良い健康的な食事を与えることが大切です。良質な総合栄養食を適正量、決まった時間に与え、規則正しい食事を心がけましょう。犬が欲しがるからといって高カロリーのフードやおやつを与えすぎるのは注意が必要です。さらに歯周病関連の病気を予防するため、食事の後にはしっかり歯磨きをしてあげることをおすすめします。(歯磨き頻度や方法はこちら)
②運動
人間と同様、適度な運動は、体重や健康の管理に欠かせません。その点、犬にとって毎日の散歩はとても大切な時間です。犬の大きさや犬種によって必要な散歩量は異なりますが、一般的に30分〜2時間ほどの散歩が推奨されています。肥満は様々な病気の引き金になると同時に寿命を縮める要因にもなりますので、日々の散歩に加えて犬が十分運動したり遊んだりできる時間や場所を確保するようにしましょう。
③定期的に健康診断を受ける
病気の早期発見や予防のために、定期的に動物病院で健康診断を受けるようにしましょう。愛犬が6歳になるまでは年に1回、7歳以上になったら年に2回以上は定期的な健康診断を受けることが非常に大切です。元気なように見えても、きちんと健康診断を受けることで、潜在的な病気を発見し速やかに適切な治療を施すことができます。また、飼い主さんによる自宅での日々の健康チェックも非常に大切なポイントです。一番身近で愛犬を見ている飼い主さんだからこそ、気付ける異変があるかもしれません。飼い主さんが自宅で行える愛犬の健康チェックの具体的な方法に関しては、ぜひこちらの動画をご参照ください。
④ストレスフリーな環境づくり
ストレスは様々な病気の原因になることもあり、長生きの大敵です。自宅や自宅周辺の環境、他のペットによるストレスなど、何が愛犬にとって負担になっているか原因を見極めるようにしましょう。犬にとってストレスになっている原因があるなら速やかに改善し、できるだけストレスフリーで生活できるようにしてあげましょう。日頃から愛犬とのコミュニケーションやスキンシップを心がけ愛情をたっぷり注ぐことも大切です。また、愛犬に対して怒鳴ったり、叩いて叱ったりすることは関係悪化の原因になるため絶対にやめましょう。しつけをする際は褒めて教えてあげることが大切です。
⑤避妊・去勢手術を検討する
愛犬の繁殖の予定や健康状態に問題がない場合は、避妊・去勢手術を検討しましょう。愛犬に避妊・去勢手術を受けさせることによって様々な病気の予防につながり、結果として健康的に長生きすることができると言われています。メスの犬については避妊手術をすることで、性ホルモンの分泌が減少し免疫機能の抑制が緩和されることで、感染症にかかるリスクの減少に役立ちます。ただし、避妊・去勢手術をするとホルモンの影響で太りやすくなることや、全身麻酔による手術のリスクなどある程度のデメリットがあることも覚えておきましょう。
避妊・去勢手術のタイミングとしては性成熟を迎えるまでの生後6〜7カ月頃が一般的ですが、成犬でも手術は可能です。できるだけ愛犬の負担を軽減するために、避妊・去勢手術の適切なタイミングを動物病院で相談することをおすすめします。
まとめ
犬の年齢を人間の年齢に換算し平均寿命を知ることで、それぞれのライフステージに合った健康管理ができます。そしてそれは愛犬が元気に長生きしてくれることにもつながるでしょう。大切な愛犬の日々の健康チェックを欠かさないようにし、動物病院のサポートも受けながら大切な家族としてできるだけ長く一緒に過ごせるよう心がけることが大切です。